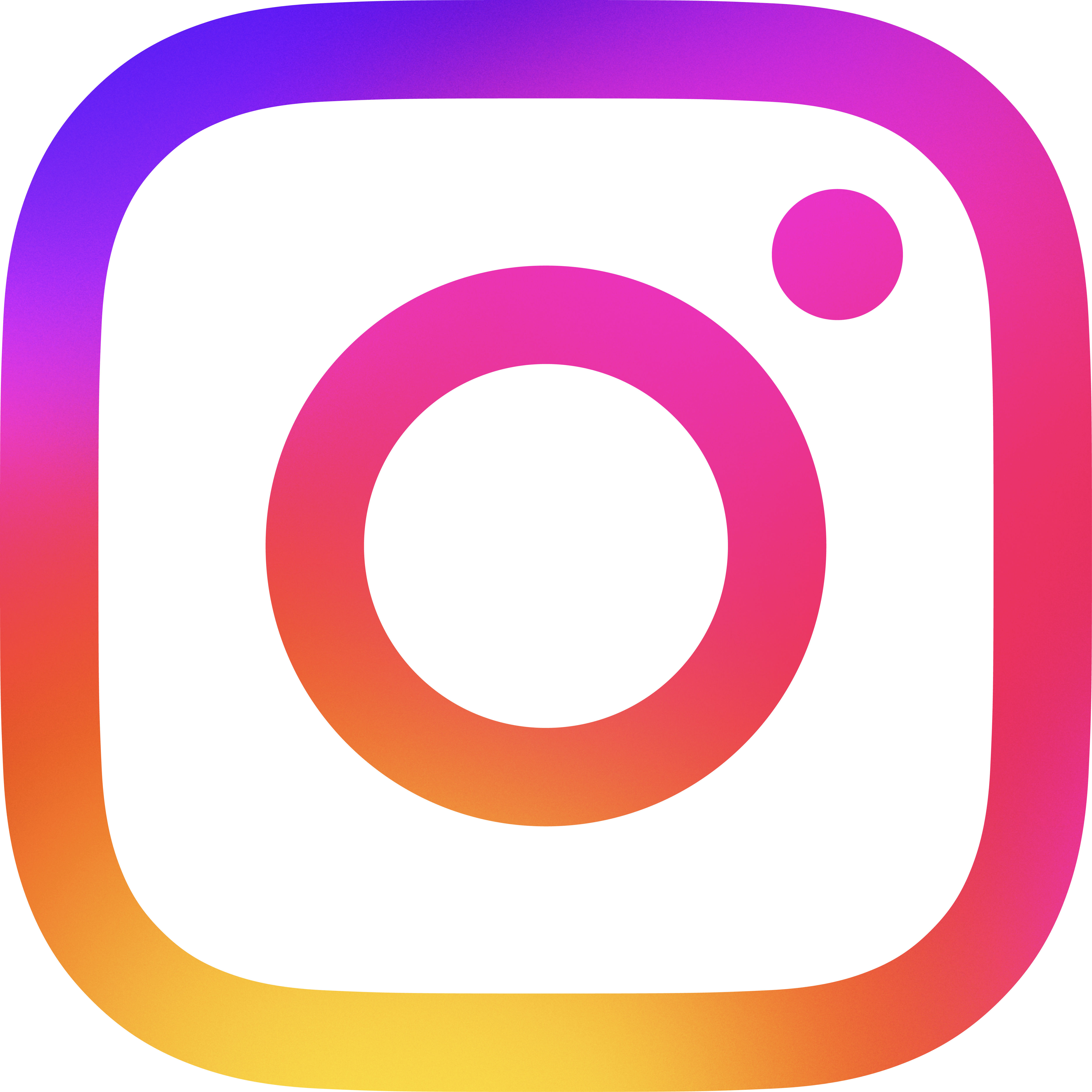【フラり対談】株式会社ベルシステム24
このコーナーでは、「トップランナー」であり「変革者」であり「インフルエンサー」でもあるゲストの方々と、目指すことや苦労話などを気負わないトークで展開しています。今回のゲストは、コンタクトセンター事業を中心に企業と生活者との接点を最適化する多彩なソリューションを展開しているベルシステム24の執行役員、加藤 寛氏です。デジタルCX本部の本部長として、コンタクトセンターでの生成AIの活用に先駆的に取り組む加藤氏と、AI技術の可能性についてさまざまに意見を交わします。

生成AIによるナレッジの抽出と活用で切り開く
コンタクトセンターのあるべき近未来

ベルシステム24は、コンタクトセンターのアウトソーサーとして40年以上の歴史を有する業界のパイオニアです。年間で約1,300社超の多種多様な業種・業態の企業に対してコンタクトセンターのアウトソーシングサービスを提供し、圧倒的な運用実績を積み上げてきました。今日では、国内36拠点、海外はベトナム、タイ、台湾でコンタクトセンターを展開し、国内では約2万席の業務スケールを確保しています。そうした同社では、労働人口の減少やデジタル化の加速に起因したコンタクトセンターにおける人材不足の問題を抜本的に解消すべく「生成AI」と「ヒト」が効果的にコラボレートするハイブリッド型コンタクトセンターの実現に取り組んでいます。その取り組みをリードするベルシステム24の執行役員でデジタルCX本部 本部長の加藤 寛氏に、リードプラス代表取締役社長の堀 裕が話を伺いました。
新たな成長・発展のために生成AIによる接客の形式知化に乗り出す
リードプラス社長 堀 裕(以下、堀):このたびは対談にお付き合いいただき、ありがとうございます。
また、運営をご支援させていただいている「コンタクトセンターの森」でも、大変お世話になっております。2024年10月は過去最高トラフィックを記録するなど、本サイトの注目度の高さを日々体感しております。
本日は、現代のビジネスリーダーの誰もが、どう使うかを思案しているであろう「生成AI」をメインテーマにして、同技術の活用に力を注いでいる加藤さんに、さまざまなお話をいただこうと考えています。よろしくお願いします。

リードプラス株式会社
代表取締役社長
堀 裕
ベルシステム24 執行役員 加藤 寛氏(以下、加藤氏):承知しました。こちらこそよろしくお願いします。

株式会社ベルシステム24
執行役員
デジタルCX本部
本部長
加藤 寛氏
堀:早速本題に入ります。まずお聞きしたいのは、ベルシステム24が生成AIの可能性をどうとらえているかです。私自身は、生成AIに触れたとき大きな衝撃を受けたのと同時に、これまでのデジタル技術にはない「人間味」を強く感じました。この「ヒトのように機能するデジタル技術」によって、従来のデジタル技術がもたらしてきた効率化とはまた別の大きなイノベーションがビジネスの世界で巻き起こるのではないかと考えています。御社ではどうなのでしょうか。
加藤氏:当社でも、そうした生成AIの可能性を強く感じています。だからこそ、生成AIをコンタクトセンターのあり方を変容させるコアの技術として位置づけ、本腰を入れて活用に取り組んでいるわけです。
ただ、当社がこの技術をどうとらえているかを語る前に、なぜ当社がAIに関心を寄せるようになったのかについて簡単に振り返りたいのですが、よろしいでしょうか。
堀:もちろんです。
加藤氏:私が当社に入社したのは2017年のことです。その当時、ベルシステム24におけるコンタクトセンター事業の「強み」として、「秘伝のタレ」の話をよく聞かされました。
堀:「秘伝のタレ」ですか?
加藤氏:そう「秘伝のタレ」です。これは、長年のコンタクトセンター事業を通じて当社が培ってきた接客(顧客対応)のノウハウを指しています。
堀:なるほど。確かにそのノウハウは、老舗料亭の「秘伝のタレ」と同様に、コンタクトセンター事業における差異化の源(みなもと)と言えますね。
加藤氏:そうだと言えます。しかし老舗料亭のそれと違うのは、当社の「秘伝のタレ」はあくまでも無形のノウハウである点です。この無形のノウハウをいかに可視化し、モデル化をするかが重要です。
近年、日本は労働人口が減少し、コンタクトセンターも人材不足に直面しています。これらの問題を解決するためにも「秘伝のタレ」、あるいはそれに類する無形のノウハウを形式知化して、再利用性・再現性を高めようと考えたわけです。
堀:なるほど、理解しました。その取り組みの中でAIの活用を着想したわけですね。
加藤氏:そのとおりです。より具体的には、コンタクトセンター事業を通じて蓄積されていく通話データをAIにより自動でナレッジとして形式知化し、誰でも、あるいは機械でも活用できるようにしようと考えたわけです。その分析の道具立てとして当社が最終的に選んだのが、生成AIでした。
堀:生成AIを選ばれた最大の理由はどこにあったのですか。
加藤氏:最大の理由は、先ほど堀さんが指摘されたような生成AIの凄さ、つまりは、この技術の人間味です。
ご存じのように、生成AIは非構造データである自然言語や文脈を解釈し、あたかもヒトの感情や置かれた状況を理解しているかのように、ヒトの心に寄り添うかたちで対話できます。それが、この技術と、これまでのデジタル技術との決定的な違いです。「この技術なら、秘伝のタレに類する無形のノウハウを形式知化する、あるいはモデル化することができる」と判断し、生成AIの活用へとつながったわけです。
堀:なるほど、理解できました。ただ、コンタクトセンターのアウトソーシングサービスを通じて蓄積されていく通話データは、基本的にベルシステム24のサービスを使う顧客企業の持ち物です。そうしたデータを御社がビジネスに活用することに同意する顧客企業は限られると思えるのですが。
加藤氏:確かに、当社が自分たちの利益追求のためだけに通話データを使おうとするならば、それを容認するお客様企業はないでしょう。ただし、当社では基本的に、お客様企業の利益のために通話データを活用しようとしています。ゆえに、通話データに対するお客様の「施錠(ロック)」を開けることができるわけです。
通話データの活用に関するこうしたアプローチや考え方は、そのまま2024年6月における「生成AI Co-Creation Lab.」(以下、ラボ)の創設につながりました。また、生成AIを活用したコンタクトセンターの自動化ソリューション「Hybrid Operation Loop」の開発にもつながっていったのです。

生成AIによるコンタクトセンターの変革をパートナーとの共同でサポート
堀:先ほど言及されたラボと、「Hybrid Operation Loop」について、少し詳しくご紹介いただけますか。
加藤氏:まず、ラボについてですが、これを発足する前の2023年6月に、当社では「Generative AIプロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトは、当社として生成AIをどうとらえ、向き合っていくかの統一見解を生むための取り組みでした。このゴールに向け、生成AIの「現在地」を正確に把握すべく、100件程度の通話データのサンプルを使いながら、生成AIに通話を要約させたり、通話内容からテーマやVOC(Voice Of Customer)を抽出させたりしました。そして、ヒトがこれらの作成・抽出を行った結果との比較評価を行いました。
同時期に世の中では、生成AIを使ったシステムのPoC(概念検証)がさかんに行われるようになりました。ところが、数々のPoCが次の段階、つまり事業化ないしは本格運用のフェーズにはなかなか進まず、PoCに携わっていたIT企業の間からは「PoCばかりで、生成AIシステムの市場が一向に立ち上がろうとしない」といった“嘆きの声”が多く聞かれていたのです。そこで、IT企業とともに生成AIの市場を創ろうという事を大義に、ラボを立ち上げました。
堀:そのラボは具体的にどのようなサービスを提供するのでしょうか。
加藤氏:ラボの役割を一口に言えば「お客様企業のために、コンタクトセンターにおける生成AIの活用をパートナー各社と共同でサポートしていく」です。つまり、コンタクトセンターの運用に関して豊富な実績とノウハウを持つ当社が「ハブ」となりながら、生成AIの開発・提供を担うIT企業(デジタルプラットフォーマー)やシステムインテグレーター、データマーケティング専門企業などの力を結集し、お客様企業のコンタクトセンターに適した生成AIシステムを提案したり、お客様企業と共同で開発したりするのが、ラボのミッションとなります(図1)。
図1:「生成AI Co-Creation Lab.」のサービス体制イメージ

堀:コンタクトセンターに特化した生成AIソリューションを提供する体制として実に頼もしいものですね。
加藤氏:加えて当社では、これまで培ってきたオペレーター育成のメソッドを活用しながら、生成AIによる顧客対応の精度を高めたり、マーケティングでの活用が可能なかたちにデータを加工したりするなど、生成AIの多様な活用方法も検討していきます。そして、ヒトと生成AIがそれぞれの特性を生かしながらコラボレートするハイブリッド型のコンタクトセンターを実現し、究極的には「コンタクトセンターオートメーション」を目指していきます。
堀:「オートメーション」といえば、「Hybrid Operation Loop」もコンタクトセンターの自動化を実現するソリューションです。「Hybrid Operation Loop」の仕組みについても教えてください。
加藤氏:「Hybrid Operation Loop」は、通話データからナレッジベースを自動生成する機能を日本で初めて搭載したソリューションです。
本ソリューションの大きな特長は、生成AIによる回答精度が95%以上見込めるため、従来に比べて飛躍的に高められている点にあります。実のところ、コンタクトセンターにおける生成AI活用の最大の障壁は、AIの回答精度が低く、実用レベルを満たせないことでした。従来は、システムイングレーターがいくら頑張っても回答の精度を80%程度にしか高められなかったのです。
堀:「Hybrid Operation Loop」は、その限界を大きく打ち破ったわけですね。その高い回答精度は何によってもたらされたのですか。
加藤氏:回答精度の低さの根本原因は、生成AIが学習に使うナレッジデータ、ないしはナレッジベースの品質が悪いことです。「Hybrid Operation Loop」は、その問題を「生成AIが通話データから高品質なナレッジベースを自動生成する仕組み」によって解決したわけです。

また、「Hybrid Operation Loop」では、情報の「類似性」と「関連性」の双方での検索を組み合わせた手法を取っています。これも、生成AIの回答精度を高めることに大きく貢献しています。
さらに「Hybrid Operation Loop」の場合、生成AIによる学習・判断・認識の際に、ヒトを介した確認・フィードバックを行うようにしています。こうして生成AIによる自動化とヒトによるチェックを適切に組み合わせることで「ハルシネーション(=AIが事実とは異なる情報を使用して回答を生成してしまうミス)」を最小限に抑えた運用の実現を目指しているのです。
図2:「Hybrid Operation Loop」における運用のループ

革新技術の活用をためらう心の壁をどう乗り越えるか
堀:ここまでのお話を聞いて改めて思ったのですが、御社は革新技術の取り込みが非常に早く、かつ、それを事業の強化にしっかりと役立てています。確か、AI音声認識技術「AmiVoice」もかなり前に採用され、製品に取り込まれていると記憶していますが。
加藤氏:ええ、おっしゃるとおり、当社では2020年にクラウド型コンタクトセンターシステムの「BellCloud+®(ベルクラウドプラス)」をローンチし、翌2021年から同システムと連動するクラウドサービスとして「AmiVoice ® Communication Suite」の提供を始動させています。
堀:革新技術に対するそうしたスピーディな対応は、実のところ、非IT系の一般企業にはなかなか難しいものです。生成AIに限らず、データを戦略的に活用すること、あるいはDXを推進することに二の足を踏んでいる企業は少なくありません。
加藤氏:堀さんはその背景理由をどう見ていますか。
堀:理由は大きく2つあると見ています。1つは、社内の各所にデータが散在し、かつ各所のデータがサイロ化していることです。これにより、例えば顧客理解を深化させるために収集・活用すべきデータが何であり、そのデータソースがどこにあるかが見えづらくなり、それを見ようとするだけで相当の苦労と手間がかかってしまいます。もう1つは、DXの取り組みを推進できるようなIT人材が不足していることです。加藤さんは、この辺りの問題をどう解決していけばよいとお考えでしょうか。

加藤氏:まず大切なのは、世の中の流れを経営陣が理解することです。というのも、データのサイロ化の解消やデータ統合基盤の構築、そして革新技術の導入は、経営陣の強力なサポートがなければ前に進まないからです。したがって、仮に現行の経営陣では世の中のトレンドを把握しきれないのであれば、それができる人材を外部から招聘するなどして、トップダウンでDXが推進できる体制を整えることが求められます。
堀:おっしゃるとおりだと私も考えます。そもそも、生成AIなどの革新技術やデータを使ったビジネスの変革、つまりDXは単純なROIでは測りきれない価値を企業にもたらすため、それを推進するかどうかは高次の経営判断が求められます。
加藤氏:そのとおりですが、対症療法的な施策としてDXを展開し、短期的な視点でそのROIを追求しようとする企業があるのもまた事実です。こうした姿勢でDXを推進していると、全体の方向感を見失い、戦略が迷走してしまいます。それを避けるためにも、DX、あるいは革新技術の活用は、中長期的な経営戦略としてロードマップと目標を明確に定めて推進すべきでしょう。
堀:まさに同感です。ところで、先にお聞かせいただいた生成AI活用のお話や、コンタクトセンターの技術動向については、冒頭にもご紹介した「コンタクトセンターの森」にも詳しく記載がありますし、各種情報も掲載されていますよね。
加藤氏:ぜひ、ご参照ください。ちなみに「コンタクトセンターの森」は、「BellCloud+」のブランディングを目指して2021年に立ち上げたメディアです。コンテンツを充実させてきたことや、リードプラスによる集客支援とコンテンツに対するアドバイスのおかげもあって多くの方々にご利用いただいています。現在は当社の技術者による寄稿を増やし、「この技術者の話をもっと聞きたい」とお客様に感じていただけるような取り組みを進めています。今後もよろしくお願いします。
堀:こちらこそ、よろしくお願いいたします。「ユーザ企業参画型プログラム」と言う新たなアプローチで、より実践的な生成AI活用を目指す「生成AI Co-Creation Lab」の今後にも大いに期待しております。本日は、興味深いお話しをお聞かせいただきまして、ありがとうございました。

※本ページの内容は 2025年2月時点での情報をもとに制作しております。